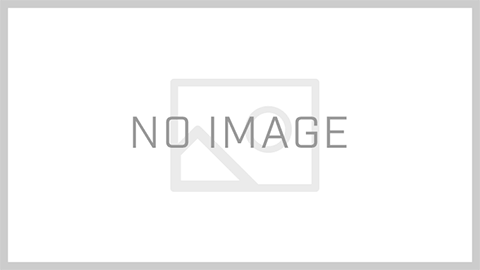大村はまさんをご存知だろうか。
中等国語教育の実践・研究者(1906~2005)として、書くことを通して学習者の考える力・自分で学習する力の育成をはかってきた国語教師。
戦後は机も椅子も、教科書も黒板もない教室で、新聞・雑誌をせっせと切り抜き、学習材料にしたそうだ。
私は大村さんの著書「灯し続けることば」を読むと、ふとまた教員に戻りたい、と思ったりします。
この中でとても印象に残ったくだりを抜粋して紹介します。
「伸びようという気持ちを持たない人は、子どもとは無縁の人です」
子どもは、高いものにあこがれ、自分をそこまで成長させよう、前進させようとひたむきに願っています。身の程を忘れてと言いたいほど、伸びよう、伸びたいと思っています。その切ないほど伸びたい気持ちと、研究や研修を通してこそ、私たちは共感していけるのです。学ぶことの苦しみ、そして少しの喜びを、子どもと同じように感じられるのです。そういう魂を持っていれば、世代を超えていつまでも子どもと共にある、と言えるのではないでしょうか。
「種を蒔くほうが大切です」
子どもはほめることが大切です。でも、いいことがあったらほめようというのではなく、ほめることが出てくるように、ほめる種をまいていくことを考えたいと思います。
「子どもほど、マンネリが嫌いな人はありません」
子どもは新鮮さに感動します。私自身が、新しいものへの小さな不安と期待を持ちつつ、子どもに向けてその教材を提供している、それが子どもを動かすのです。
「優劣のかなたで、学びひたる体験をさせたいのです」
誰より優れているとか劣っているとか考えるのは、一種のゆるみです。そんな優劣を超えた、いわば優劣のかなたで自分の学習にひたることが大切なのです。優劣など頭に浮かぶひまのない世界にまで、教師は子どもを連れて行かなくてはいけないのだと思います。
「年が小さいから、教え子として、ここに座っているにすぎません」
この子たちは自分をはるかに乗り越えて、未来の国をつくってくれる人なんだ、そういう敬意をもって、子どもという宝物に接していかなくてはならないと思います。
「教師は渡し守のようなものでしょう」
子どもが卒業していったら、私のことは全部忘れて、新しい学校、新しい友達に慣れて、新しい自分の世界を開いていってほしいと思います。教師は渡し守のようなものだから、向こう岸へ渡した子どもたちにはさっさと歩いていってほしいのです。「どうぞ新しい世界で、新しい友人と、新しい先生について、自分の道を開拓していって」と思いつつ、子どもを見送っています。
大村はま著「灯し続けることば」より抜粋
「教師は渡し守」のくだりは、私にちょっぴり反省を促します。
どうしても退院して元の学校に戻った子、卒業していった子のその後が心配になったものです。
転出していった子が外来のたびに職員室に遊びに来て慕ってくれるのが嬉しかったものです。
今どうしてるとか、将来は○○しようと考えてるとか話してくれるのが楽しくて。
渡し守、確かにその通りだ、と120%納得するけれど、やっぱりこれだけは私には無理だな、と思ったりもします。
教職を離れた今も大村はまさんの考え方はいろいろな場面で指針となっています。